管工事の施工管理を公的に行う上で必要な資格である、管工事施工管理技士は国家資格です。
その中でも、1級管工事施工管理技士は管工事の施工を管理する上での最たる資格です。
今回は1級管工事施工管理技士の資格について、合格率や難易度、試験内容などについて解説します。
2級と業務内容の違いや年収、転職事例などもご紹介します。
1級管工事施工管理技士の合格率と難易度
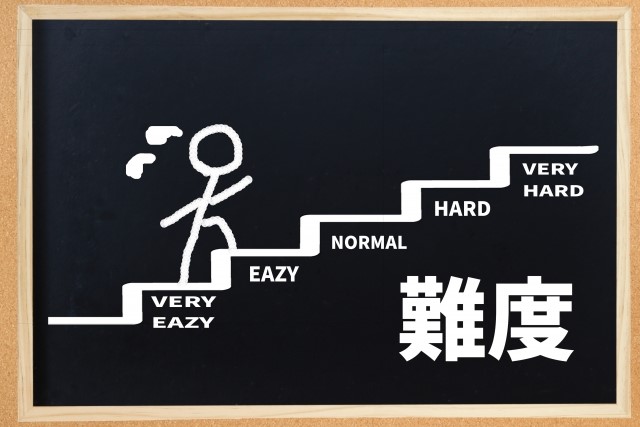
それでは初めに合格率から難易度を見てみましょう。
第一次検定
第一次年度別合格率
| 年度 | 合格率 |
| 平成30年度 | 33.2% |
| 令和元年度 | 52.1% |
| 令和2年度 | 35.0% |
| 令和3年度 | 24.0% |
第一次検定は年度によってばらつきがありますが、平均して合格率は36%程度となっています。
令和3年度は24.0%で、過去10年間で最も低い合格率となりました。
しかし、難関とまではいかない難易度です。
基礎固めをしっかり行い、出題されている意味を理解することができていれば独学であっても問題なく合格できます。
準備期間をしっかり設けることが重要です。
第二次検定
第二次検定年度別合格率
| 年度 | 合格率 |
| 平成29年度 | 52.7% |
| 平成30年度 | 52.7% |
| 令和元年度 | 61.1% |
※令和3年度は執筆時点で未公表
合格率としては平均して50%を超えており、低くはありません。
一次検定に合格できる知識があれば知識としては十分です。
しかし二次検定はすべて記述式の解答を求められるため、誤字脱字による減点があります。
また意味が伝わらない解答でも減点となるため、ある程度の文章力が必要です。
実際の試験では解答後に入念に確認を行い、ケアレスミスをなくしましょう。
経験記述問題があるのも二次検定の特徴です。
自身の経験した現場について自身で解説を行うという問題ですが、明確な答えがあるわけではないため、独学では難しいと感じる可能性もあります。
そういった場合は講習会などで添削を行っているので受講をするのもひとつの手です。
1級管工事施工管理技士の試験内容
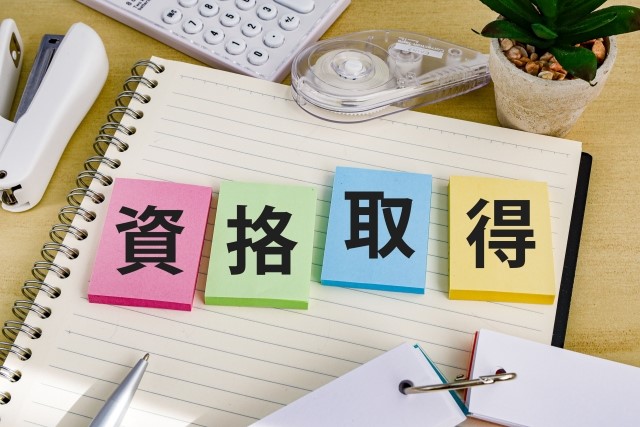
第一次検定
一次検定には下記の特徴があります。
-
・マークシート方式
・正答率60%以上かつ「施工管理法(応用問題)」の正答率50%以上で合格
・試験時間は午前の部2時間半、午後の部2時間の2部構成
試験科目としては「機械工学」「施工管理方法」「法規」などについてが出題されます。
また令和3年度の試験制度改定により名称が「学科試験」から「第一次検定」となりました。
第二次検定
二次検定には下記の特徴があります。
-
・記述方式
・正答率60%以上で合格
・試験時間は2時間45分
試験科目としては監理技術者として「管工事の施工管理方法を適確に行うための知識」、「設計図書で要求されている設備性能を確保するための知識、必要機材の選定、配置を適切に行う知識」が問われます。
一次検定と同じく令和3年度から「実地試験」から「第二次検定」へと名称が変更されました。
1級管工事施工管理技士取得の勉強方法
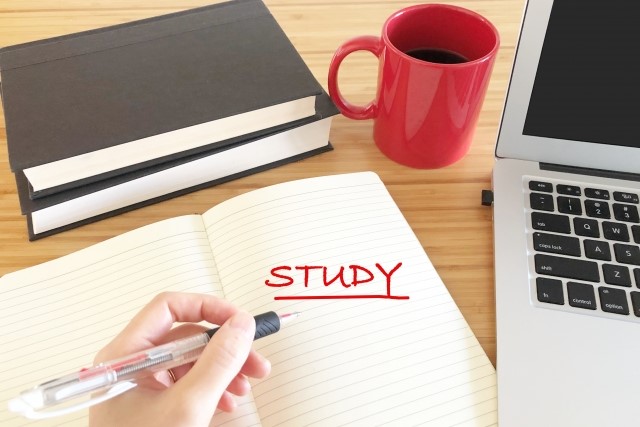
①まずは、勉強時間を確保することが大事です。
1級管工事施工管理技士取得に必要な勉強時間は、最低でも75〜100時間程度とされています。
1日1時間であれば3ヶ月以上、2時間であれば1.5ヶ月程必要です。
毎日しっかり勉強時間がとれる環境であれば問題ありませんが、仕事をしている場合はなかなか勉強時間を確保できない時期もあるでしょう。
そういった状況を見越して早めからの準備を心がけましょう。
②参考書を1冊分読みましょう。
勉強の進め方としては、1級管工事施工管理技士の参考書を1冊分読み切りましょう。
1冊読み切ることで、出題傾向が見えてきます。また自身の苦手としている箇所も見えてきます。
完全に理解することはないので、まずは読み切り、分からなそうな箇所をメモしておくなど、今の自分と合格までの距離の分析を行いましょう。
③繰り返し過去問を解きましょう。
参考書を読み切り、ある程度分析ができたら、あとは繰り返し過去問を解きます。
前年度だけではなく、過去5年分程度までさかのぼり、何度も解いていきましょう。
過去5年分を完全に正答できる程度まで行います。
また二次検定の記述式の解答例もしっかり頭に入れておきましょう。
施工管理技士検定の関門と言われているのが、経験記述問題です。
試験当日に慌てることのないよう、予め記述する現場を決めておき、現場情報を暗記し、どのような問題が出たとしても対処できるようにしておきましょう。
この明確な答えのない、経験記述ですが講習会などを受講することで、講師による添削を受けられるのでどうしても不安な場合はおすすめです。
1級取得後の2級との業務内容の違いについて
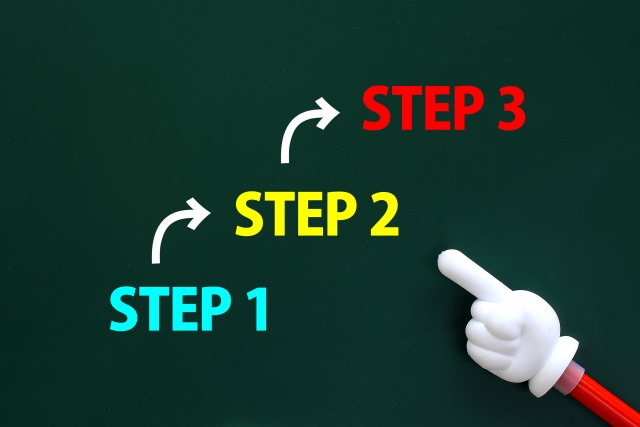
1級管工事施工管理技士を目指す方のほとんどが、既に2級を取得済みで日々施工管理を行っている方だと思います。
1級を取得することでこれまでの業務との違いはあるのでしょうか。
1級と2級の大きな違いは監理技術者になれるか、です。
監理技術者とは下請契約の工事請負代金が4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)の場合に配置が必要となる人です。
この監理技術者は1級取得者でなければなりません。
よって大きな現場では1級管工事施工管理技士の配置が必須となるわけです。
1級取得後は今までより大きな現場を任されることが多くなります。
1級管工事施工管理技士の年収について

1級管工事施工管理技士の年収は平均して500〜700万円前後です。
所属会社や経験年数などにより、年収は変わります。中には1,000万円を超える大手企業もあります。
また企業によっては資格手当というものが毎月支給されますので、資格を取得するだけでも年収は上がります。
1級管工事施工管理技士の資格手当の平均は6,000〜10,000円程度です。
1級管工事施工管理技士を活かした転職事例
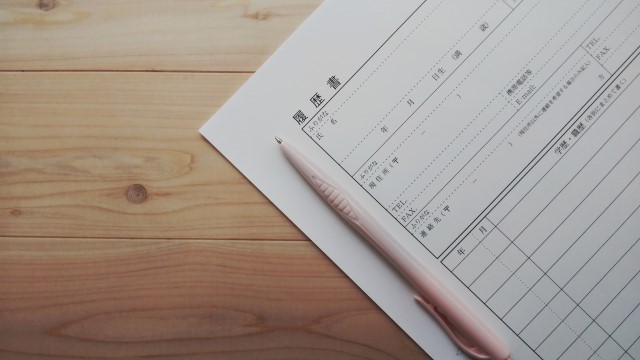
1級管工事施工管理技士の資格を取得し、それを活かして転職した事例について紹介します。
①地元設備会社から大手サブコンへ転職
-
高校卒業後に地元の設備会社へ就職し、日々戸建住宅の給排管工事の施工管理を行っていました。
毎日小さな現場ばかりで飽きてきたところ、いつしか大きな現場も経験してみたいと考えるようになり、全国的に展開しているサブコン会社へ転職を決めました。
転職後に1級管工事施工管理技士の資格も取得することができ、今では念願だった大きな現場で施工管理をしています。
大変なこともありますが、給与も前職より上がったので満足しています。
②管工事施工管理の経験から土木施工管理技士へ転職
-
元々1級管工事施工管理技士として管工事のサブコンで勤めていましたが、ふと見つけた求人で建築会社で1級管工事施工管理技士有資格者の募集をしていました。
土木工事である造成工事に付随する下水工事から施設内の配管工事までを一括で管理できる人間を探しているとのことで、自分にピッタリだと思いました。
待遇も現職よりも良くしてもらえたので即転職しました。
③サブコン勤めから個人事業主として独立
-
会社員というしがらみから抜け出したく、これまでの経験を元に思い切って独立しました。
前職で培った人脈を頼りに施工管理が不足している現場で施工管理を請け負っています。
自分次第で年収を上げていくことも出来、休みなどを自分で設定することもできます。残業など強制されることもありません。正社員とは違った柔軟な働き方を実現することができます。
まとめ
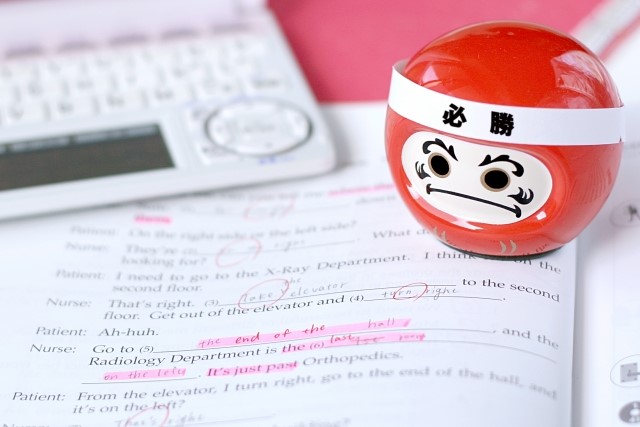
今回は1級管工事施工管理技士の資格の難易度について解説しました。
合格率はそこまで低くはないので、勉強次第と言えるでしょう。
この記事を参考にして合格への近道にして頂ければ幸いです!
施工管理の求人を探すには

資格や経験を活かして、施工管理で転職をお考えの方は、キャリケンの完全無料転職支援サービスをご利用ください。
転職活動における当サービス独自のノウハウを特別にお伝えします。
業界唯一の伴走型エージェントが、全国各地の10,000件以上ある求人から最適な求人をご紹介します。
是非一度、ご相談ください!



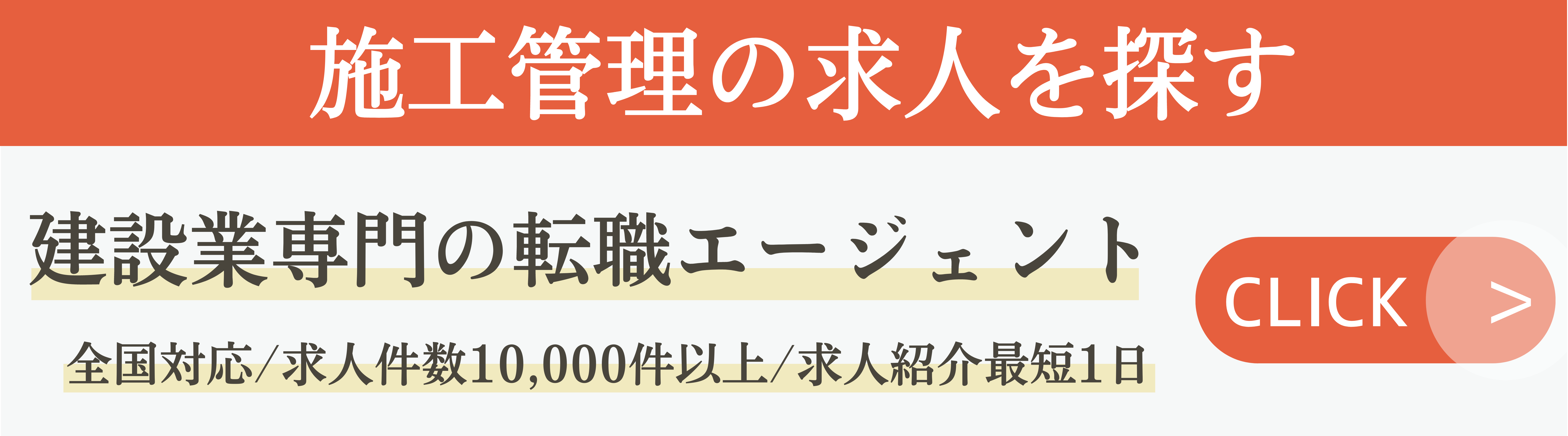

最新-min.png)

