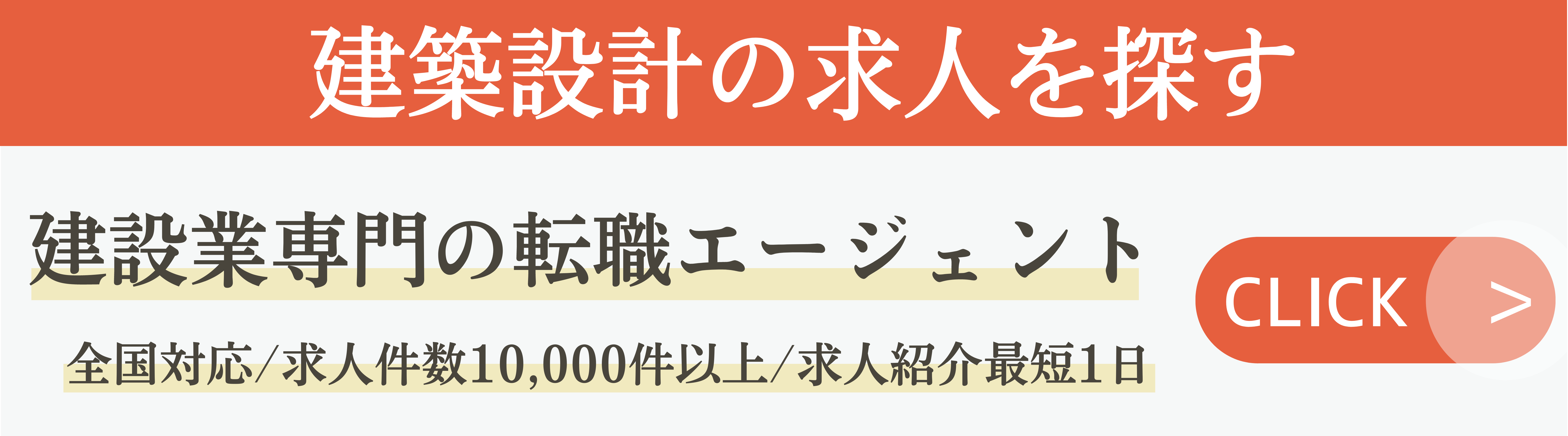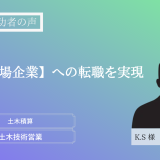建築士が取得が難しい資格であることは世間的にも知られています。
平均の合格率も著しく低く、特に一級建築士は10%程度です。
そのため、建築士を目指している人の半数以上は専門学校や通信講座を利用しています。
しかし、少数ですが建築士を独学で取得する方がいるのも事実です。
今回は建築士の資格を独学で取得するための勉強時間や勉強方法などについて解説します。
仕事と両立しながら勉強を続けるコツや資格取得者の成功事例なども紹介します。
建築士とは

それでは建築士の資格について解説する前に、まずは建築士とはについて解説します。
建築士の仕事内容
建築士とは建築物の設計、および工事監理を行う仕事をする者です。
施主が求める建物のイメージを図面やパース図などを作成し具現化させる仕事です。
またその設計物が実際の工事が始まった際に設計通りに施工されているかを確認する工事監理を行うことも仕事です。
公的に建築設計を行うことを認められるには国家資格である建築士の資格が必要です。
資格には一級と二級があります。
一級と二級の違い
建築士には「一級建築士」と「二級建築士」があります。
違いは設計・監理ができる建物の規模です。
二級建築士
建物高さ13m、軒高9m以下(全ての構造)
延床面積1,000㎡以下(木造の場合) 延床面積100㎡以下(RC造、S造その他)
階数 3階建てまで(全ての構造)
一級建築士
全ての建造物に制限なし
二級は建物高さ、延床面積、階数に制限が掛けられますが、一級は規模制限がありません。
そのほかは大きな違いはありません。業務内容に関しても全く同じです。
しかし、資格取得難易度はどちらも高いです。
建築士資格は独学で取得できるのか

建築士取得者の大多数が予備校や通信講座を活用して、資格取得を実現していますが、中には独学で取得する人も一定数います。
果たして独学で取得することは本当に可能なのでしょうか。
二級の難易度と必要な学習時間
二級の平均合格率は20%前後と建設系国家資格の中でも比較的高めですが、学習時間と学習方法を見誤らなければ独学取得は充分可能です。
学習時間としては、大学などで建築に関する科目を修めている人は500時間、未修学者は700時間程度が必要と言われています。
半年〜1年前を目安に学習開始を検討しましょう。
特に製図に関しては、入念な準備が必須です。
一級の難易度と必要な学習時間
一級の場合、二級以上の難関となっています。
平均合格率は10%を切っている年度がほとんどで建設系に限らず国家資格の中でも難易度が高い資格です。
独学取得はかなり厳しいですが、不可能ということはありません。
綿密な学習計画を立て、効率的に学習を積み重ねていくことが重要です。
必要な学習時間は二級取得者など一定の知識を有している人で700〜1000時間程度、未修学者で1500時間程度です。
1年半〜2年以上前から計画を立てることが理想です。
二級と同じく製図の習熟には時間が必要です。
二級の学習方法

建築士の試験は、学科試験と製図試験にわかれています。
毎年7月頃に学科試験が行われ、合格者のみが9月もしくは10月頃に行われる製図試験へと進むことができます。
これは二級、一級どちらも同じです。
学習スケジュールを立てる
学科試験の合格基準は施工管理技士などの試験と違い、全ての科目で合格基準点に達さなければ合格となりません。
よって苦手科目を捨てるという選択ができないため、全ての問題に対応できる力を備える必要があります。
| 出題数 | 合格基準点 | |
| 学科Ⅰ(建築計画) | 25問(各1点) | 14点以上 |
| 学科Ⅱ(建築法規) | 25問(各1点) | 14点以上 |
| 学科Ⅲ(建築構造) | 25問(各1点) | 14点以上 |
| 学科Ⅳ(建築施工) | 25問(各1点) | 14点以上 |
| 合計 | 100問(100点) | 60点 |
まずは試験日から逆算して「この期間までにこの科目をマスターする。」など期限を設定することが合格への第一歩です。
過去問を何度も繰り返す
二級建築士は各科目で基本知識を問われます。
直近5〜7年分の過去問集を何度も繰り返すことで自然と基本知識が培われますので、問題に対する対応力が付きます。
ポイントは年度ごとに過去問を解くのではなく、スケジュールで定めたマスターすべき科目ごとに進めていくことです。
「建築計画」の期間であるならばそれ以外の科目は飛ばして「建築計画」のみにフォーカスすることで効率よく学んでいけます。
建築法規の対策をする
建築士の試験には学科Ⅱの建築法規があります。
他の科目と違い法規は法令集の持ち込みが許されています。
そのため、試験では法令集から答えを見つける速度が必要です。
対応策としては読みやすい法令集を早めに入手し、過去問で出た問題に対し解説を見ながらマーカーやアンダーラインを引いていきます。
この作業を行うことで、検索速度が上がります。
また法規の出題傾向を把握することができるので、対策も取りやすくなります。
製図試験対策
学科試験の2ヶ月後にはすぐに製図試験が待っています。
製図試験は手描き図面を作成しなければなりません。
普段から手描き図面を作っている方であればそれほど必要ないかもしれませんが、ほとんどの方がCAD図に慣れている現代では対策が必要です。
試験では与えられた条件を基にプランニング(エスキス)を行い、製図を行います。
まずは手描きのスピードアップが最重要ですので、学科試験の学習と並行して過去問の模範解答の模写作業を毎週1本ずつこなし手描き図面に慣れていきましょう。
学科試験合格後はプランニング(エスキス)の対策を行います。
プランニングは経験を積んでいくことが重要ですので、過去問を学科試験以上に年度をさかのぼって取り組んだり、過去問以外にネットで公開されている課題に取り組んだりすることで対策ができます。
製図試験の3日前には課題が公開されるので忘れず確認し、プランを練っておきましょう。
一級の学習方法

一級の学習方法も基本的には二級の学習と大きな違いはありません。
しかし、一級は二級以上に高度な専門知識が必要となりますので、一筋縄ではいきません。
学習スケジュールを立てる
一級も二級同様、全ての科目で合格点を出しつつ、総合点も合格点に達しなければなりません。
| 出題数 | 合格基準点 | |
| 学科Ⅰ(計画) | 20問(各1点) | 10点以上 |
| 学科Ⅱ(環境・設備) | 20問(各1点) | 11点以上 |
| 学科Ⅲ(法規) | 30問(各1点) | 16点以上 |
| 学科Ⅳ(構造) | 30問(各1点) | 16点以上 |
| 学科Ⅴ(施工) | 25問(各1点) | 13点 |
| 合計 | 100問(100点) | 87点 |
※令和3年度試験合格基準点
一級は二級より科目が1つ増えています。
まずは網羅的にマスターできる期間を設定していきましょう。
またマスターした科目であっても必ず復習する期間も設けましょう。
学習後から時間が経過すると忘れてしまいます。
一級はそれほど膨大な知識が必要です。
過去問を何度も繰り返す、法規対策を行う
二級同様、過去問を何度も繰り返す学習および法規対策を行います。
一級の場合は、できれば過去11年〜15年分までを行うのが理想です。
理由としては様々な問題に慣れておくことと、近年の試験傾向として、11〜15年前の問題が出題されやすいことが分かっているからです。
反対に直近の問題はほとんど出ないので、直近5年分は模擬試験用にとっておくのもひとつの方法です。
法規に関しても二級同様に法令集をカスタマイズしておきます。
一級の場合法規の問題配分が多く得点源となりやすいので、怠らずに対策を行いましょう。
模擬試験で時間配分を把握する
一級の試験はとにかく時間との勝負となります。
どの問題にどれだけの時間を割けるのかを把握することは非常に重要です。
残しておいた過去問の直近5年分を活用し、どの問題で時間が掛かっているのか明確にしましょう。
製図試験対策
一級も二級同様に学科試験の約2ヶ月後に製図試験が行われます。
基本的な対策は二級と変わりありませんが、二級に比べ一級は課題の規模が大きいです。
集合住宅や公共施設などが多く出題されており、当然製図に時間が掛かりますので、二級以上の手描き図面のスピードが求められます。
また設計条件も複雑になっており、プランニングもしっかり練り込む必要があります。
二級以上に学科試験勉強の合間に製図への対策は行っていくべきです。
仕事と両立しながら学習を続けるコツ

学生であれば学習をすることが本分のため、あまり参考になりませんが、仕事をしつつ建築士の資格を目指している方もいるでしょう。
しかし、仕事の傍ら学習を行うのは時間的な制限もあり、物理的に難しいと思われる方もいるかもしれません。
ここでは、仕事をしながらでも学習を続けていくためのコツについて紹介します。
退社後は必ず寄り道
仕事が終わって自宅に戻ると疲れがどっと来てしまい、「今日の仕事終わり!」といった状態に陥りやすくなってしまい学習を行う意欲が湧かないことが多いです。
そこで退社後には必ずカフェなどに立ち寄って少しでも学習時間を作るという習慣を作ってみてはどうでしょうか。
例え気が進まない日があったとしても、一度行ってしまえば意外と集中していることに驚くはずです。
朝活で学習時間確保
いつもより、2時間早く起きて学習時間を物理的に作ってしまうのもおすすめです。
人は朝が一番エネルギーが溢れています。
インプット効率が最も高く、学習するには一番良い時間とされています。
また、朝活を行うことで規則正しい生活も実現でき、その後の本業でも目がしっかり覚めているのでいいスタートが切れます。
とても気分良く一日を迎えられるでしょう。
モチベーションを保つ
モチベーションを保ち続けることは重要ですが、とても難しいことでもあります。
仕事が忙しくなれば資格取得のことなど二の次となってしまい、結局諦めてしまうこともあるかもしれません。
最も有効な保つコツは資格取得を目指していることを人に伝えてしまうことです。
目標を達成できなければ「あいつは口だけだ」と言われてしまうプレッシャーをあえてかけることで、モチベーションを保つことができます。
また、自身のレベルの進捗を見える化し、目標とのギャップを客観的にみることもモチベーションを保つのに効果的です。
独学での資格取得成功事例・資格取得を活かした成功事例

高校卒→独学で二級建築士取得!
大変だったことは、大学に進学していたので勉強する時間はたくさんあったのですが、遊びの誘惑も多くモチベーションを維持することでした。
予備校などを活用すれば良かったのかもしれませんが、当時はお金もあまりなく費用がもったいなかったので独学一択でした。
私がしたことはとにかく周りの友人達に二級取得を公言することでした。
合格を目標にするのではなく、有言実行を目標に変えてモチベーションを維持し続けました。
二級建築士→独学で一級建築士取得!
一級建築士の受験資格は既にあったので、過去に2回資格取得を目指しましたが、いつも仕事の繁忙期と重なってしまい受験をすることなく途中で挫折しています。
それまで私は仕事が終わったあとに自宅に帰り入浴後に勉強をしていたのですが、どうも仕事のことばかり頭に残り、全く集中できず結局は持ち帰った仕事をしている始末でした。
そこで取り入れたのが朝活です。
通常毎朝6:00に起きていたのを4:00に起きることにし、2時間を勉強に充てました。
早朝は夜と比べかなり集中することができ、挫折することなく毎日続けることができました。
おかげで受験することもでき、無事一発で合格できました。
二級建築士→独学で一級建築士を取得し年収アップ!
それまでは二級建築士として在籍していましたが、昨年独学で一級建築士を取得しました。
取得をしたことで変わったことは、大きなプロジェクトに一員として入れてもらえたことです。
また体感的にですが、自身の意見も通りやすくなったように感じます。
そしてなによりも大きかったのは年収が上がったことです。
二級建築士の頃は年収420万円ほどでしたが現在は年収500万円になりました!
独学は正直きつかったですが、がんばって取得して本当に良かったと実感しています。
施工管理技士→独学で一級建築士を取得し大手ゼネコンへ転職!
数々の現場を担当させて頂いていましたが、だんだんともっと大きな、もっと難しい現場に挑戦したい気持ちが強くなり、大手ゼネコンへの転職をしたいと思うようになりました。
しかし、大手では中途採用が厳しいことが分かっていたので、何か付加価値が必要と思い独学で一級建築士の取得を目指しました。
製図にはかなり手こずりましたが、なんとか取得することができ、運がよかったのかあまり苦労することなく、転職をすることができました!
現在の会社は先進的過ぎて、毎日が刺激的です。これからがんばっていきます!
まとめ

今回は建築士の独学で取得する方法などについて解説しました。
建築士は特に一級は世間的にも地位が認められている仕事です。
取得するには大変な努力が必要ですが、その努力以上のメリットが多くあります。
少しでも建築士を目指す人の力になれていれば幸いです。
建築設計の求人を探すには

資格や経験を活かして、施工管理で転職をお考えの方は、キャリケンの完全無料転職支援サービスをご利用ください。
転職活動における当サービス独自のノウハウを特別にお伝えします。
業界唯一の伴走型エージェントが、全国各地の10,000件以上ある求人から最適な求人をご紹介します。
是非一度、ご相談ください!