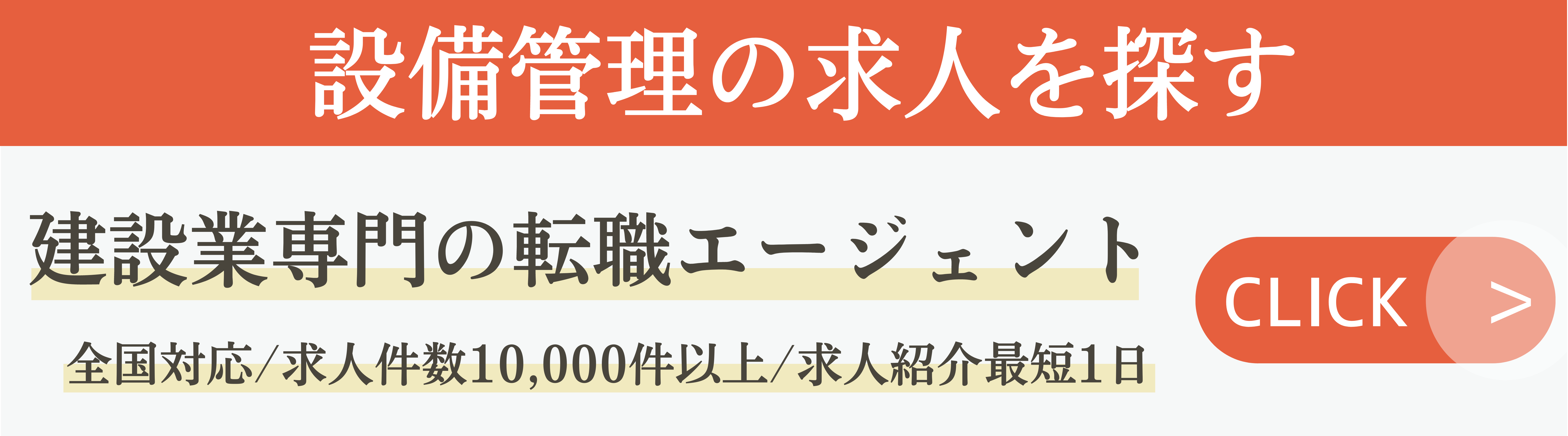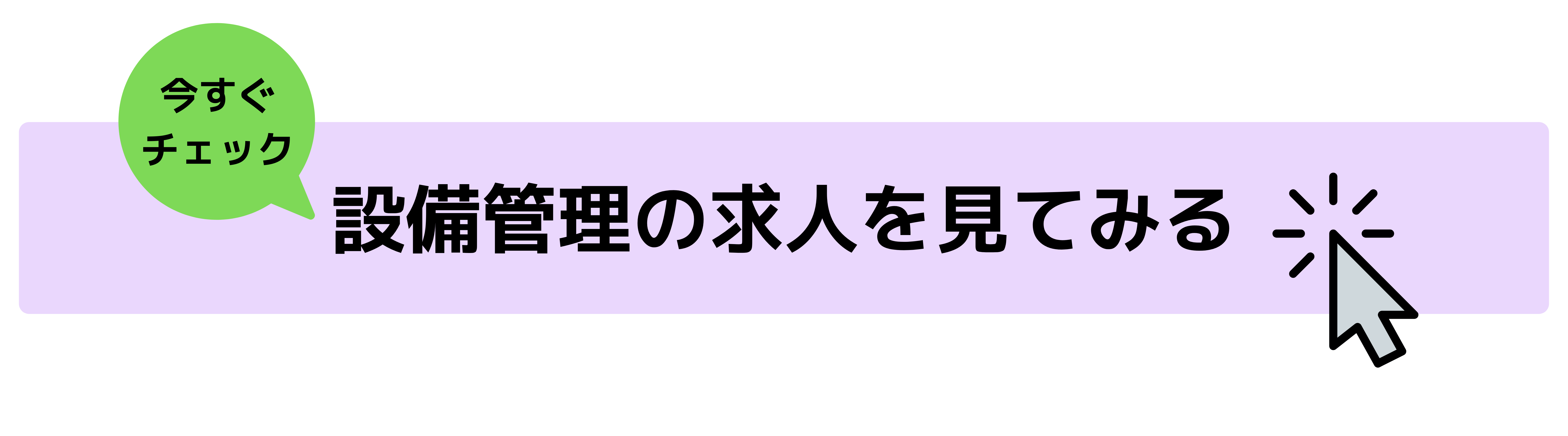近年の産業・経済の発展に伴い、電気設備の利用は年々増加しています。
また、使用電圧においても、高電圧化している傾向があります。
こうした状況の中、感電事故などによる死亡災害は後を絶ちません。
感電事故を防止するため、電気設備の整備や保守業務の従事者は、安全に業務を遂行するための知識と技能を有することが重要です。
そのため、労働安全衛生法では、電気取扱業務の従事者に対し、特別教育を行うことを義務付けています。
参考:労働安全衛生法 第59条|https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-6-0.htm
電気取扱者とは

資格及び仕事内容
電気取扱者とは、充電電路や電路における支持物の、敷設・点検・修理を行うために必要な資格です。
低圧・高圧・特別高圧のそれぞれにおいて、以下の業務に当たる場合、電気取扱者の特別教育が必要です。
「高圧(直流にあつては750Vを、交流にあつては600Vを超え、7000V以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7000Vを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては750V以下、交流にあつては600V以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」
引用:労働安全衛生規則 第36条 第4号|https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#532https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm
低圧・高圧・特別高圧電気取扱者とは

低圧電気取扱者
低圧電気取扱者は、低圧(交流では600V以下、直流では750V以下)における充電電路の敷設、もしくは修理の業務、または、配電盤室・変電室などの区画された場所に設置する、低圧の電路における充電部分が露出している開閉器の操作業務を行うための資格です。
高圧電気取扱者
高圧電気取扱者は、高圧(交流では600V以上7000V以下、直流では750V以上)における充電電路や電路の支持物の敷設・点検・修理もしくは操作の業務を行うための資格です。
特別高圧電気取扱者
特別高圧電気取扱者は、特別高圧(交流及び直流において7000V以上)における充電電路や電路の支持物の敷設・点検・修理もしくは操作の業務を行うための資格です。
資格取得のメリット

・講習を受講することで取得できる
特別教育の修了証発行による資格のため、国家資格と違い試験はありません。
作業に必要な技術的資格ではなく、電気取扱に関する危険性のある業務に従事する者に、事業者が実施する法定教育です。
・安全に関する知識が得られる
現場で作業を実施するために必要な、安全に関する知識を得ることができます。
過去に発生した災害や事故をもとに、危険または有害な作業を安全に遂行するための知識、技術の教育を受けられます。
・電気工事士資格がなくても電気取扱業務に従事できる
充電電路の支持物を敷設する作業や、点検・修理に関する作業を行う事が可能になります。
電気工事士資格を取得していない者であっても、特別教育を受講することによって、一部作業に従事することが可能になります。
資格概要

受講資格
事業者は、労働者を雇い入れた際に、労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、その従事者に対する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならないと定められています。
つまり一定の危険有害業務に従事する労働者に対し、事業者が実施する法廷の教育です。
一般社団法人安全衛生マネジメント協会や、労働基準協会連合会、電気保安協会などが、事業者の代わりに特別教育を行っています。
18歳未満でも受講は可能ですが、年少者労働基準規則によって18歳未満では、高圧もしくは特別高圧の業務に従事させることができません。
そのため、受講終了後18歳までは修了証が発行されない場合もあります。
参考:労働安全衛生法 第59条|https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-6-0.htm
受講内容
低圧電気取扱者
学科講習:7時間
低圧電気の基礎知識
低圧電気設備に関する基礎知識
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
低圧活線作業及び活線近接作業の方法
関係法令
実技講習:7時間
低圧活線作業及び活線近接作業の方法
高圧・特別高圧電気取扱者
学科講習:11時間
高圧又は特別高圧電気の基礎知識
高圧又は特別高圧電気設備に関する基礎知識
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識
高圧又は特別高圧活線作業及び活線近接作業の方法
関係法令
実技講習:15時間
高圧又は特別高圧活線作業及び活線近接作業の方法
高圧・特別高圧電気取扱者の実技講習については、法定では15時間必要ですが、
実施団体によっては1時間のみ、もしくは学科のみ実施している団体がほとんどです。
実技講習は事業者で行わなければならないことが多いようです。
受講日程
事業者が特別教育を行う場合や、外部による特別教育を受講する場合によって日程はさまざまです。
受講する事業所又は、実施団体にてご確認ください。
講習を実施する機関や協会によっては、実技講習は行っていない場合があります。
また、訪問による出張講習や、オンラインによる講習を受け付けている場合もあります。
受講地
受講地は、特別講習を行う事業者、又は実施団体により異なります。
詳しくは受講を希望する実施団体へお問合せください。
受講料
低圧電気取扱業務特別講習
9000円〜21000円程度
高圧・特別高圧電気取扱業務特別講習
17000円〜26000円
電気工事士資格と電気取扱者資格の関係性
国家資格である電気工事士免状を取得している場合、電気工作物の工事に従事が可能です。
しかし、電気工事士の資格を有していても、労働安全衛生法に規定する労働災害防止に関する教育を満たすことになりません。
そのため、電気工事士の資格を取得していても、電気取扱者の特別講習を受講する必要があります。
事業者は従業員を電気設備工事に従事させる場合、安全衛生に関する教育をすることを義務付けられています。
そのため、電気取扱者資格を取得することで、現場で活躍することが可能になります。
一緒に取得しておきたい関連資格

電気工事士
第一種電気工事士及び第二種電気工事士の2種類があります。
第二種電気工事士では低圧電気工作物の工事ができる資格です。
第一種電気工事士は、高圧電気工作物の施工が可能になる資格です。
工事施工に従事するための技術資格となるため、電気取扱者特別講習によって安全衛生に関する知識を学ぶ必要があります。
認定電気工事従事者
第二種電気工事士は自家用電気工作物の工事に従事することができません。
しかし、認定電気工事従事者の資格を取得することで、自家用電気工作物の低圧部分の工事に従事できます。
認定電気工事従事者の資格を取得している場合でも、安全衛生特別講習は必要です。
安全に対する知識の教育を受けなければなりません。
電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、電気工事の施工管理を行う資格です。
安全・原価・工程・品質に関する管理を行います。
そのため、安全衛生に関する知識に関しては教育を受けなければなりません。
電気施工管理技士の有資格者であっても、事業者の行う電気取扱者教育を受講していなければ、現場での作業はできません。
電気主任技術者
電気主任技術者は、電気設備の保安や維持運用に係る、点検・保守を行う資格です。
電気のプロフェッショナルと呼ばれる資格ですが、安全衛生に関する教育は必要です。
電気取扱者は感電事故防止が目的の、事業者の法定教育です。
資格の活用事例・転職事例

事例1:取得資格を活用した事例
積算業務→現場業務に転向(年収380万円→450万円)
それまでは積算業務についていたそうです。
ですが以前から電気工事の現場に出て学びたかったそうで、現場に出るために保安協会で実施している講習に申し込み、電気取扱者特別講習を受講しました。その意気込みが上司に買われ、憧れていた現場業務に就くことができたそうです。
図面と向き合っていた積算業務と違い、現場でしっかり体験して学べることがとても幸せだと話していました。
事例2:他資格も取得して成功した事例
施工管理技士として活躍(年収450万円→600万円)
電気取扱者特別講習を受講し、安全衛生に関する意識が高まったとのこと。
電気工事をより安全に、円滑に遂行することが目標となり、施工管理として活躍したいと考えました。そのため電気工事施工管理技士の資格を取得し、現在は監理技術者として勤務しておられます。
年収も高くなり、モチベーションも上がったと嬉しそうでした。
事例3:転職事例
サブコンから大手ゼネコンにキャリアアップ(年収550万円→700万円)
電気取扱者の資格を取得して以降、スキルを証明するためには資格が必要だと考えたと話すCさん。
電気工事士の資格を取得し、さらに電気主任技術者の資格を取得します。
その後キャリアアップのため転職を決意。
電気サブコンから大手ゼネコンへの転職に成功し、年収も大幅に増加しました。
資格を取得していたため、転職もスムーズに決まったと話していました。
まとめ

高圧電気より、さらに高電圧となる特別高圧は、取り扱いの危険度も高まります。
しかし私たちの生活の基盤となる電気が使えるのは、特別高圧による安定した電気の供給があるためです。
特別高圧が使用されるのは、送配電施設や変電所、または大規模な工場施設や鉄道などです。
つまり私たちの生活に密着するインフラを支えている電力です。
そうした電気を扱うために、安全に対する意識と教育は必須です。
電気を扱うことは危険性があるため、事業者は安全衛生に関する教育を行うことが義務付けられています。
感電災害や事故を防止するために、非常に重要な役割を果たしている教育となります。
設備管理の求人を探すには

資格や経験を活かして、設備管理で転職をお考えの方は、キャリケンの完全無料転職支援サービスをご利用ください。
転職活動における当サービス独自のノウハウを特別にお伝えします。
業界唯一の伴走型エージェントが、全国各地の10,000件以上ある求人から最適な求人をご紹介します。
是非一度、ご相談ください!